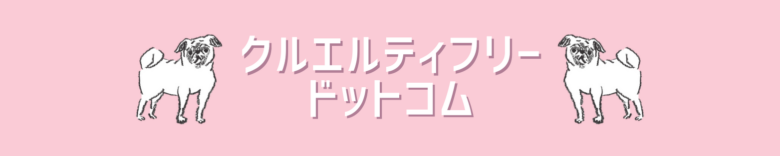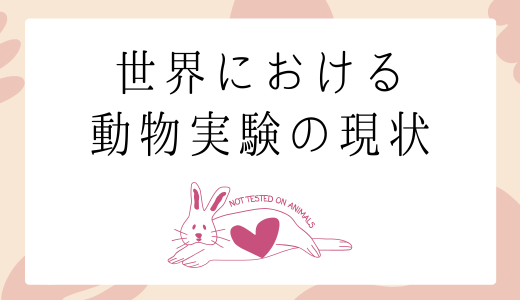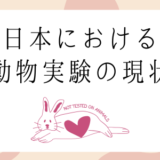動物実験は世界中で行われており、医薬品や化粧品、農薬の開発、さらには教育現場に至るまで、あらゆる場面で動物が犠牲となっています。
実際には、世界中で毎年1億9,000万匹以上の動物が苦しみながら命を落としているのです。
この現状を知り心を痛めるかもしれませんが、同時に、動物を使わない方法も急速に広がりつつあります。
本記事では、各国の動物実験の現状や規制の違い、代替法の進展状況まで、包括的にわかりやすく解説します。
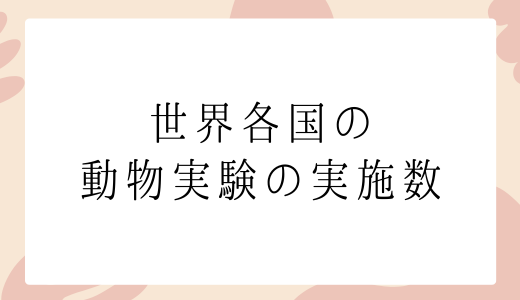
世界では、毎年1億9,210万以上の動物が科学目的で使用されていると推定されています 。
以下は、動物実験の年間使用数(推定値)を国別にまとめたものです。
| 国名 | 年間使用数(推定) |
|---|---|
| 中国 | 約2,050万匹 |
| アメリカ | マウス・ラットを含むと1,200万~2,400万匹 (公式統計では約80万匹) |
| 日本 | 約1,500万匹 |
| EU全体(27か国+ノルウェー) | 約930万匹 |
| フランス | 約210万匹 |
| ドイツ | 約170万匹 |
| インド | 公式統計はないが主要国より使用数は少ないと推測 |
世界で最も多くの動物実験が行われているのは中国で、年間約2,050万匹が使用されています。
アメリカは、法律上のカウント対象外であるマウスやラットを含めると、実際の使用数は1,200万~2,400万匹にのぼると推定され、公式統計(約80万匹)とは大きく乖離しています。
日本は世界で3番目に動物実験数が多い国とされ、年間約1,500万匹が使用されていると推定されます。
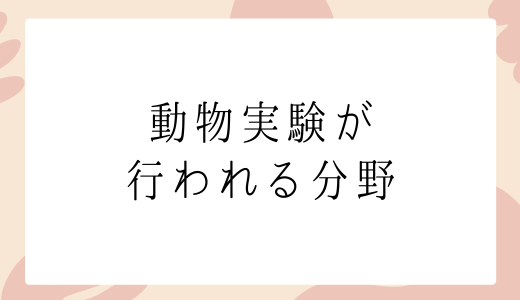
動物実験が行われる分野は大きく分けて以下の5つに分類できます。
- 基礎研究(医学・生物学研究)
- 医薬品開発・安全性評価
- 化学物質(農薬・工業化学品等)の毒性試験
- 化粧品分野
- 教育・訓練
それぞれの分野別に、動物実験がどのような規模感で行われているのかを見ていきましょう。
各国において、動物実験の大半は基礎研究や医薬品開発に利用されています。
例えば、EUでは動物実験の約半数が大学や研究機関での基礎・応用研究目的で行われており、医薬品や農薬などの規制安全性試験は全体の12%程度にとどまります。
アメリカでも、政府機関や製薬企業が疾病研究や創薬を目的に動物実験を実施しており、特に新薬開発の初期段階でマウスやサルを用いた試験が組み込まれています。
また、新薬をヒトに投与する前には、げっ歯類(マウス・ラット)と非げっ歯類(犬・サルなど)の2種類の動物で毒性試験を行うことが国際基準とされてきました。
多くの国では新薬開発=動物実験が必須という状況が続いていましたが、近年のFDA法改正などにより、動物実験の要件を緩和する動きが進んでいます。
農薬や工業化学品の登録には、大量の動物実験データの提出が求められます。
EUのREACH規制(化学物質登録制度)では、かつてウサギや魚を用いた急性毒性試験が多数行われ、問題視されていました。
発がん性評価や複数回投与試験など、代替が難しい試験では動物実験が続いており、特に中国や米国動物では新規化学物質の審査にデータへの依存が続いているのが現状です。
近年、化粧品のための動物実験を禁止する国が急増しています。
EUでは2013年に動物実験済みの化粧品販売も含めて全面禁止となり、その流れはインドやイスラエル、韓国、オーストラリアなど40カ国以上に広がっています。
一方、日本や米国では法的禁止はなく、企業の自主規制に委ねられているのが現状です。
しかし、多くの大手メーカーがクルエルティフリー(動物実験を行わない)への移行を進めており、今後さらなる禁止国の拡大が期待されています。
かつては生物学の解剖実習や外科手技訓練で多くの動物が使用されていましたが、教育分野でも動物を使わない代替法の導入が進んでいます。
例えば、米国軍では戦場医療訓練にヤギを使用していましたが、近年はシミュレーターに切り替えられました。また、日本の大学でも、解剖実習でのカエルなどの使用が減少しています。
インドでは大学教育での動物解剖を全面禁止し、デジタル教材や仮想解剖ソフトが活用されるようになりました。
近年、毒性試験分野でも代替法の導入が進み、皮膚刺激性や目刺激性の評価では動物を使用しない試験が標準化されつつあります。
しかし、ワクチンの品質試験(例:ボツリヌス毒素製剤の検定)など、一部の分野では依然として動物実験が必要とされているのが現状です。

動物実験に対する規制は国や地域ごとに異なり、完全に動物実験を禁止している国は存在しません。
特に医薬品や医学研究目的の動物実験は、ほぼすべての国で認められていますが、その厳格さには大きな違いがあります。
| 国・地域 | 動物実験の規制内容 |
|---|---|
| EU | ・実験前に政府の許可と倫理審査が必須 ・苦痛軽減措置と代替法の使用が義務 ・2013年以降、化粧品の動物実験を全面禁止 ・大型類人猿の実験も禁止(人道上の例外を除く) |
| 英国 | ・実験前に政府の許可と倫理審査が必須 ・動物実験するために資格が必要 ・規制違反には法的措置が適用 |
| アメリカ | ・一部の動物実験は規制 ・マウス/ラット/鳥類は法律上の規制対象外 ・州ごとに規制が異なり統一された厳格な管理はない |
| 日本 | ・法的拘束力のない指針による「自己点検・自己申告制」 ・政府の監査や立ち入り検査の義務はない ・研究機関や企業の自主規制に依存 ・政府の動物実験統計も不十分 |
しかし、一部の分野では規制が進んでおり、その代表例が化粧品分野です。
化粧品における動物実験は、世界各国で禁止の流れが広がっています。
| 国・地域 | 施行年 | 禁止内容 |
|---|---|---|
| EU(欧州連合) | 2013年 | 化粧品の動物実験および動物実験を行った化粧品の販売を全面禁止 |
| イギリス | 1998年 | 国内での化粧品の動物実験を禁止 |
| ノルウェー | 2013年 | 化粧品の動物実験および動物実験を行った化粧品の販売を禁止 |
| アイスランド | 2013年 | 化粧品の動物実験および動物実験を行った化粧品の販売を禁止 |
| リヒテンシュタイン | 2013年 | 化粧品の動物実験および動物実験を行った化粧品の販売を禁止 |
| スイス | 2017年 | 動物実験を行った化粧品の販売を禁止 |
| イスラエル | 2013年 | 化粧品および洗剤の動物実験を禁止し、動物実験を行った製品の輸入・販売も禁止 |
| インド | 2014年 | 化粧品の動物実験を禁止し、動物実験を行った製品の輸入も禁止 |
| トルコ | 2015年 | 化粧品の動物実験を禁止し、動物実験を行った製品の販売も一定条件で禁止 |
| 台湾 | 2019年 | 化粧品の完成品・成分の動物実験を禁止(適用除外あり) |
| 韓国 | 2018年 | 化粧品の動物実験を禁止し、動物実験を行った製品の販売も禁止 |
| オーストラリア | 2020年 | 化粧品の動物実験を事実上禁止 |
| ニュージーランド | 2015年 | 国内での化粧品用途の動物実験を全面禁止 |
| メキシコ | 2021年 | 化粧品の動物実験を禁止し、動物実験を行った製品の輸入・販売も禁止 |
| グアテマラ | 2017年 | 化粧品の動物実験を禁止 |
| コロンビア | 2020年 | 化粧品の動物実験を禁止し、動物実験を行った製品の輸入・販売も禁止 |
| チリ | 2023年 | 化粧品の動物実験を禁止し、動物実験を行った製品の輸入・販売も禁止 |
| カナダ | 2023年 | 化粧品の動物実験を禁止し、動物実験を行った製品の販売・輸入も禁止 |
EUでは2013年に、化粧品の開発における動物実験と動物実験済みの化粧品の販売を禁止し、EU加盟国(27か国)では化粧品のための動物実験が事実上不可能になっています。
この流れは、インド、イスラエル、ノルウェーなどを含む40カ国以上に拡大しており、世界的に化粧品分野での動物実験は縮小傾向にあります。
一方で、アメリカや日本では、化粧品の動物実験に関する法的禁止はなく、企業ごとの自主規制に委ねられています。
アメリカでは、一部の州で動物実験を行った化粧品の販売禁止措置が取られていますが、連邦レベルでの禁止はありません。
中国では、2021年から一般化粧品に限り、条件付きで動物試験データの提出を免除できる制度に移行しましたが、依然として動物実験が行われているのが現状です。
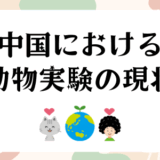 【2025年最新】中国における動物実験の現状について
【2025年最新】中国における動物実験の現状について このように、化粧品分野においては世界的に動物実験の廃止が進んでいますが、国によって規制の厳しさには差があるのが現状です。

動物実験の代替法(Alternative Methods) とは、動物を使用せずに安全性や有効性を評価する方法であり、世界的に開発・導入が進められています。
特に注目されている代替法は以下の3つです。
| 代替法の種類 | 概要 | 代表的な試験例 |
|---|---|---|
| in vitro 試験 (試験管内) | ヒト細胞や組織を培養し化学物質や薬剤の影響を分析 | ・皮膚刺激性試験 ・眼刺激性試験 ・毒性試験 |
| in silico 試験 (コンピューターシミュレーション) | コンピューターを活用し化学物質や薬剤の作用を予測 | ・毒性予測プログラム ・分子動力学シミュレーション |
| 臓器チップ (Organs-on-a-Chip) | ヒトの臓器細胞を再現した微小チップ上で生体環境をシミュレーション | ・肺チップ ・腎臓チップ ・肝臓チップ |
代替法の導入状況は国によって異なります。
EUは、1990年代から代替法の研究を推進し、世界で最も代替法の承認・普及が進んでいる地域です。
EU法では、動物実験を実施する前に代替法を使用することが義務付けられており(3Rの原則を法制化)、OECD(経済協力開発機構)を通じて皮膚刺激性試験や眼刺激性試験など、動物を用いない試験法が国際的に承認されています。
特に2010年代以降、皮膚や眼の刺激性、アレルギー性を評価する代替試験法が相次いで導入され、これらの領域では動物を使用しない試験が標準となりつつあります。
イギリスでは、1986年に制定された「動物(科学的処置)法」に基づき、動物実験が厳しく規制されており、動物実験における「3Rの原則」(置換、削減、洗練)が推進されています。
代替法を推進する主な機関としては、以下の2つが挙げられます。
- NC3Rs:動物実験における3Rの原則を推進するための国立研究機関
- FRAME:医学実験における動物実験の代替を推進する基金
近年では、人工知能(AI)やオルガノイドといった先端技術を活用した代替法の開発も進められており、イギリスは動物実験の代替法において、世界をリードする国のひとつとなっています。
近年、アメリカでは動物実験の代替法導入が進んでいます。
2022年には「FDA近代化法2.0」が成立し、新薬の承認審査で動物実験データの提出義務が緩和され、コンピューターモデリングや臓器チップなどの先進的な実験手法が認められるようになりました。
化粧品分野でも動物実験に対する規制が強化され、ニュージャージー州を含む8つの州では、動物実験を用いて開発された化粧品の販売が禁止されています。
世論調査によれば、動物実験を道徳的に許容できると考えるアメリカ人の割合は減少傾向にあり、2023年の調査では初めて半数を下回りました。
環境保護庁(EPA)は、2035年までに化学品開発での哺乳類動物実験を廃止する目標を掲げており、動物実験削減に向けた取り組みが進行中です。
- https://sustainablejapan.jp/2020/07/02/epa-animal-testing/51508
- https://animals-peace.net/experiments/gallappoll2024.html
- https://eleminist.com/article/1795
- https://tabi-labo.com/305926/wt-fda-stops-obligation-to-animal-test
- https://animals-peace.net/animalexperiments/us-animal-usage-statistics
- https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/31220/law020201900301.pdf
日本では、1989年に「日本動物実験代替法学会」が設立され、代替法の研究開発と普及に努めています。
また、日本動物実験代替法評価センター(JaCVAM)は、化学物質の安全性評価における動物実験の3R(削減、苦痛の軽減、置き換え)を促進し、新たな代替法の公定化を推進しています。
これらの組織の活動により、細胞培養や非哺乳動物、非脊椎動物、コンピューターシミュレーション(in silico)などを活用した代替法の研究が進展しています。
中国では、2025年1月には、日本企業が動物実験代替法を用いた新原料の申請を成功させるなど、代替法の実用化が進んでいます。
また、毒性学や環境科学の分野で、動物を用いない代替法に関する国際的な協議が中国で開催されるなど、科学者間での代替法に対する関心も高まっています。
しかし、全体としては、動物実験の代替法導入は進行中であり、引き続き改善が求められています。
インドは教育分野における動物実験の代替において、世界でも先進的な取り組みを進めている国の一つです。
大学助成委員会(UGC)が全ての大学に対し、学部および大学院レベルでの動物学や生命科学の授業において、動物を使った解剖および実験の中止を正式に指示しました。
科学教育においては、コンピューターシミュレーションやインタラクティブ教材、実物そっくりの模型など、非動物的な学習手段が有効であるとされています。
UGC関係者の試算によれば、この措置により年間で最大1,800万匹もの動物が解剖から救われる可能性があるとされています。
世界では今も、多くの動物が実験に使われています。
しかし、同時に動物を使わない未来をめざす動きも、確かに広がっています。
化粧品の分野では、すでに40か国以上が動物実験を禁止しており、多くの企業が「クルエルティフリー」な製品づくりに取り組んでいます。
また、科学技術の進歩により、動物を使わない試験法もどんどん現実的になっています。
私たち個人は、動物実験をしていないメーカーを利用して応援するなど、できることからやっていきましょう!